

実は街は植物で溢れている。彼らは色、カタチ、ニオイなどで「ここにいるよぉ」と静かなるメッセージを出している。そこには時として胸を打つドラマがあったりもする。そんなやもすると見過ごしてしまいそうな愛すべき彼らにあまり肩肘張らずにゆる~いカンジでスポットライトを当てる。日々の「あれ何だろう?」という好奇心に素直に向き合うブログ。












あたりが代表的な特徴。
1は茎を持って指先で転がしてみよう。カクッカクッと角張っているのが実感できるハズ
2は見ての通り、葉っぱが常にペアになって茎から出ている
3は花、茎、葉などあらゆる場所に産毛のように細かい毛が生えている
今回の写真はちょっと縮小率を下げてあるので上の2枚は毛が生えているのがみえると思う。
他にも花の形が以前述べたことがある 左右相称 になっていたりする。(3月14日ユリオプスデージー)
シソ科にはおなじみものがかなり多くて、シソは言うに及ばずラベンダー、ローズマリーなんかもそう。
お刺し身の薬味でホジゾがでてきたら見てみてねん。









と、以上6項目。
中には あたりまえ、常識というものもある(というか全部そうかも)けど、3番目の席とりでちょっと思い出したことが。
平成バブルでわいた頃、僕はサラリーマンをしていた。当時新入社員の4月の大仕事として、この花見の席とりがあった。寒いさなかゴザを引いて昼過ぎくらいから場所を確保する。トイレにいく間に席がどうにかなりやしないかなんてことでハラハラしながら1日を過ごす。
仕事を終えて皆が到着する頃にはカラダが冷え切っていて、ビールなんかより暖かいコーヒーください、などど涙目で訴えたものだ。
そんなことがフツーにあった、良くも悪くも破天荒、ノンビリ、お気楽極楽な時代を思い出してちょっと懐かしくなった。



さえあれば、ウマイ カプレーゼができるのですね。当たり前か。
火を通して調理するわけではないので素材が大切といいたいのですね。
コショウも挽きたてが香りがたってウマイし。
そういった場合、自宅で摘みたてのフレッシュなバジルを使うと美味しさはアップするのは自明の理というもの。
めでたくバジル君は胃袋におさまり、長らくお伝えしてまいりましたバジルニュースは一旦お開きに。
お付き合い有難うございました。

昨日の陽気はいったい・・・。
気持ちヨカッタ。半袖はモチロンだが、思わず短パンを引き出しの中から探し出してはこうと思ったけど、これはさすがにやめておいた。
靖国神社に散歩がてら寄ってみた。
そういえばここ靖国神社には サクラの標準木 というのがあって東京のサクラの開花宣言はこのサクラで出されると聞いたことがあったので、どれどれどれがその有名なサクラだ? と野次馬的にそのサクラを探した。
聞くと靖国神社には3本の標準木があるそうで、そのうちの一本がこの能楽堂わきのこれ。
まだツボミは硬かったけど、かなり膨らんでいるようだった。
開花宣言も遠くないな、と。
開花宣言はこのサクラが 5~6輪咲いたらだされるそうなのだが、お恥ずかしながらこの5~6リンを「輪」ではなく「厘」だと思っていた。
なぜならサクラは「××分咲き」という表現をするではないか。で開花なのでホンのちょっと咲いているのを気象庁のエキスパートの方が見分けるとすれば「分」のひとつ下の単位「厘」ではないかと思うのは道理だと思うのだけど。
どうやって5厘を見極めるのかは大いに興味があった。
全体の花のつぼみの数を数えて分母を導いて・・・・、などと変に感心していたのだけど、ナーンダである。

この前間引きをするときに、間引いたバジルを捨てるのはもったいないので鉢上げした、と書いたあとどうなってるか。
ご覧になって分かるかと思うのだけど、もともと育てていたポケットティッシュのような容器のバジル君たちはスクスクと育ち、葉っぱはもう食べごろです。
かたや植木鉢に植えたほうは、葉っぱのサイズが半分くらいで色も濃い緑色をしている。
明らかにアンハッピーなシチュエーションと申せましょう。
でも、たった一週間やそこらでこれだけの差がでるっていうのはある意味スゴイと思いませんか?
ちょっとショック。
良かれと思ってやったのに。
で、どうしてか?と原因をつらつらと考えてみるに、
①植え替えのときに細かいヒゲ根を傷つけてしまった
②植え替えのときに使った土にいらぬものが入っている
かな、と。
①は、仮にそうだとしてもそろそろ根を再生して元気を取り戻すころである。現にアンハッピーそうではあるが、枯れちゃいないので根にはあまり問題がなさそうに思える。
一番疑っているのが②である。今回鉢上げのときに使ったのはホームセンターで買ってきた「種まき・さし芽 緩効性肥料入り」という土。都会のベランダでは、不本意ながらこういったものを買わざるをえないのである。
で、何でそう思っているかというと、バジルの葉っぱの色とサイズ。
ハッピーなバジル君に比べると明らかに葉っぱの緑の色が濃くて小さい。植物、とくにバジルのように葉っぱが柔らかい草本は「肥料やけ」のように過剰な肥料の影響を受けやすいのだ。
人間でもオトナ、特にオッサンはユンケル黄帝液をガブ飲みして「パワーついたっ!」と満足顔だろうが、赤ん坊にそれをしたらどうだろうか?
改めてその買ってきた土の袋を詳細に見てみると、「醗酵海藻土入り」「貝化石入り」「緩効性肥料」などとアレコレ入っている。百歩譲って前者ふたつがいわゆるオーガニックものであったとして、緩効性肥料はどうも化成肥料のようである。化成肥料は即効性があるけど、それがバジルのように柔らかい植物には利きすぎちゃうのだと思う。
化成肥料を使ったこのバジルを食べるというのは、自分が育てたものとはいえちょっとだけ二の足を踏んでしまう。
世の中オーガニック流行りなのもうなずけるのであった。
*多分ポケットティッシュ状のバジル栽培キットの土にもなんらかの化成肥料が入っていると思うけど。




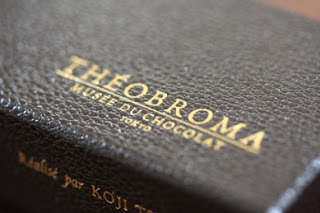






と植物のオンパレードである。さらに厳密にいえば、醤油もダイズからということで、植物界からの堂々のエントリーである。
かくして主役のかつおを控えめな植物たちで脇をかためるという図になる。
素晴らしいじゃぁありませんか。
もしこのひとつでも欠けるとかつおの旨さは活きてこないと思うのだけど。
そういった意味ではつまのダイコンにも敬意を表して残したりしてはいけません。
イヨッ!!名脇役!!